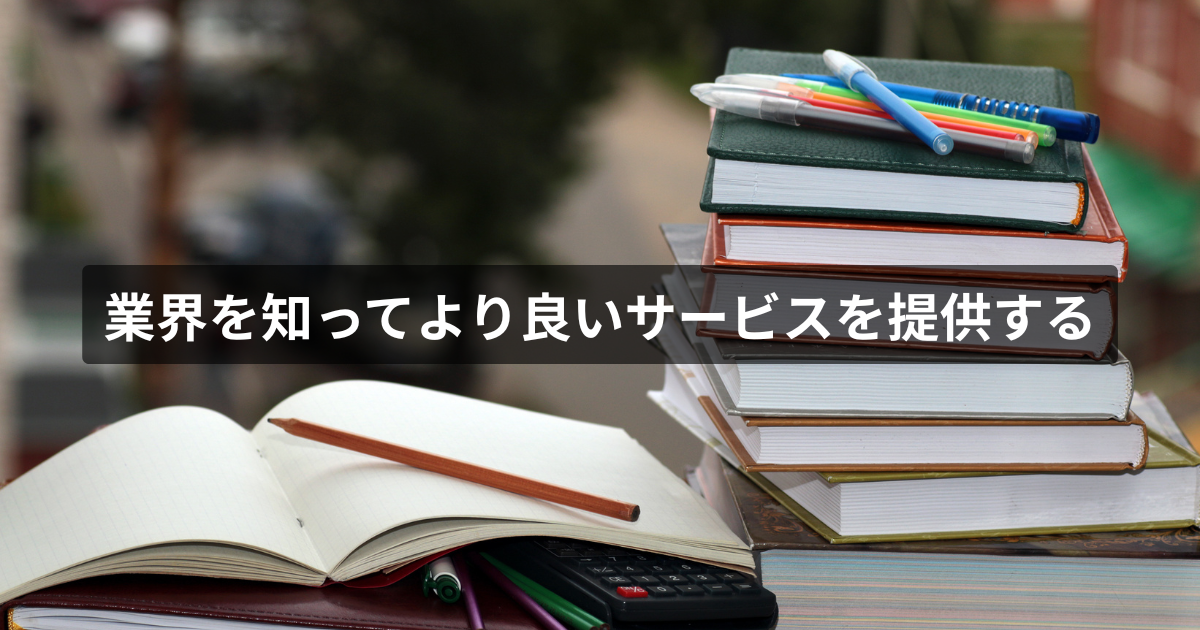税理士として独立・開業すると、税務・会計だけでなく、学ぶべきことが一気に増えてきます。
今回は、私が独立後に強く感じた「業界を知ることの大切さ」について書いてみます。
税務・会計の知識だけでは事務所は回らない
開業してから、私は「本業以外の知識の必要性」を強く感じました。
- ホームページやSNSを活用した集客
- 新規顧客への営業スキル
- 職員との連携を高める組織づくり
- AIやクラウド会計を活用した業務効率化(DX)
これらは勤務時代に経験する機会は少なく、もちろん資格試験では教えてくれません。
勤務時代は税務・会計の知識を深めることに注力できましたが、開業して事務所を経営する側となった今、それだけをやっているわけにはいきません。専門外のことであっても自分がやる以外ほかにやってくれる人はいません。事務所の価値を高めるには欠かせないスキルです。
そして、その一環として私が注力しているのが、「税理士業界の研究」です。
意外と知らない、隣の税理士事務所
私の事務所は、税理士事務所が集中しているエリアにあり、半径500m以内に10件以上の税理士事務所があります。
しかし、そのうち代表と直接お話したことがあるのは半数程度。どんな分野が得意なのか、どんなサービスを提供しているのか、どんな経営哲学をお持ちなのか、知る機会はほとんどありません。
ブランディングに成功している有名な事務所は例外として、いわゆる「街の税理士事務所」は表に出ることが少なく、お互いの情報がほとんど共有されていないのが現状です。
「ライバルだから話したくないのでは?」と思われがちですが、実際にはそうではないと考えています。
多くの税理士が
- 日々の業務に追われている
- 情報交換する機会がない
- 自分のやり方に集中している
- 今さら聞きづらい
- そもそも興味がない
ため、他の事務所の情報を得る時間も機会もないというのが本当のところではないでしょうか。
実際、事務所経営について聞いてみると皆さん「同業者には話さない」ということはなく、親切に教えてくれます。
私自身、以前勤めていた事務所のやり方をベースに、自分なりに工夫しながら事務所を経営していますが、「そもそも、このやり方で本当にいいのか?」を常に自問自答しています。
「業界を知る努力」は何のため?
私が他の税理士事務所の取り組みを知りたいと考える理由は、お客様により良いサービスを提供したいからです。
税理士業務は年々変化しています。特にここ数年の変化は凄まじいものがあります。
- AI技術の活用
- 会計ソフトの進歩
- DXへの取り組み
- コンサル的な支援への期待
自分のやり方に固執していては、こうした変化に対応できません。
私が実践している「業界研究」
① 他事務所への訪問・見学
会合やセミナーで知り合った先生にお願いして、実際に事務所を見学させていただくことがあります。
お願いすると意外と皆さん快く承諾してくださり、包み隠さず教えてくださいます。
私が開業して間もないというのも事務所見学をお願いする際の心理的ハードルを下げている気がしています。
事務所の雰囲気、スタッフの働き方、IT環境、価格帯など、ネットでは得られないリアルな情報をお聞きすることができます。
② SNSでの情報収集
最近はX(旧Twitter)やInstagramを積極的に活用する税理士も増えてきました。
他の先生方の考え方、発信の仕方、日常のつぶやきからも多くの学びがあります。
③ 業界誌の購読
『月刊実務経営ニュース』などの業界専門誌には、注目の事務所の取り組みやインタビュー記事が満載です。
成功事例や新しいサービスのヒントを得られ、自分の業務に応用できるものが多くあります。
気づきを得て改善する
私は税理士になって10年以上経ちますが、「業界を知った気になっていただけ」だったと痛感しています。
業界の動向や他の税理士の取り組みを知ることで、自分の視野の狭さやより良いサービスのヒントに気づくことができます。
業界研究が、自己満足で終わってしまってはいけません。
他の事務所のやり方をヒントに、自分のサービスを改善し、「お客様により良いサービスを提供する」という気持ちを忘れずに続けていきたいと考えています。